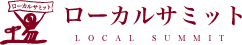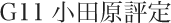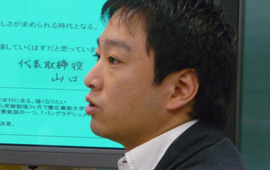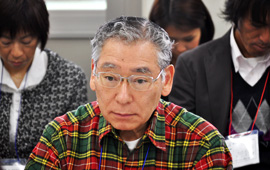- 現在のページ
-
- ホーム

- 活動報告

- 2010年 第3回ローカルサミットin小田原

- G11 小田原評定
- ホーム
いのちの生成発展の場である地域を考える際に重要な11のテーマを設定しました。そのテーマごとにグループに分かれ、分科会形式で議論をしました。新しいものさしとは?
小田原ならこんなことができるのでは?という二つのポイントについて4時間たっぷりと話し合いました。
オリエンテーション
2010年10月23日 13:00-14:00 鈴廣かまぼこの里
まずは参加者約270名が昼食を食べながら、午後のグループセッションの内容と進め方を共有しました。全員が一堂に会する姿は壮観でした。その後、次に会場までバスで移動しました。
グループセッション
2010年10月23日 15:00-19:00 星槎湘南大磯キャンパス
11のテーマの中から登録時に選択したテーマの教室に入りました。まず、モデレータから進め方について話があり、次にパネリストの皆さん(グループごと4名から6名)に一人15分程度でご自分の活動の報告や問題提起のプレゼンをしていただきました。星槎学園という思索と議論に最適な環境にも恵まれ、それぞれの教室では聴衆の皆さんも巻き込んでの熱い議論は4時間を超えました。まとめ役のモデレータからは大変だった。でも楽しかったという声しきりでした。各グループでまとめてもらった結論を翌日のまとめセッションの準備のために事務局が回収した時のモデレータ各位の感想でした。
各セッションの登壇者、セッション内容はこちら。
* 各セッションの模様を録画したDVD並びに録音テープ(各4時間11種類)がございます。DVDは、録音テープの価格は決定しだいお伝えします。
| 1 |
いのち活かす「ものづくり」東海道五十三次小田原宿は寄木細工、小田原漆器、小田原鋳物といった職人のまちであった。それらに加えて、ほとんど知られていないが、その昔、小田原は 全国の七割の生産を誇る竹ものさしの一大産地だった。足柄の山々の竹林を利用し、伝統技を継承する職人たち。しかし、今は職人はいなくなり、小田原産の竹ものさしはもうない。 |
|---|---|
| 2 |
いのち生きる「商流」城下町として栄えた小田原。市が立ち、近郊の農山村の山の幸、前浜の豊かな海の幸、職人の技が産む洗練された物産が集まる、人とモノの交流拠点であった。そこは生産する者と消費する者どおしお互いの顔が見えたはずだが、今は・・・。 |
| 3 |
いのち輝く「あきない」道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は戯言である。(二宮翁夜話より)」という教えは時代を超えて新しい。CSRという言葉を待つまでもなく、私たちの先人から学ぶべきのいかに多いことか・・・。 |
| 4 |
いのち繋ぐ「金融」二宮尊徳は、報徳思想のもと、農村の疲弊を克服せんと報徳金という形での無利息金融の仕組み(五常講)を編み出し、世界初の信用組合をつくった。そんな先人の知恵に学ぶ、地域で顔の見える暖かいお金が廻るしくみとは・・・。 |
| 5 |
いのち移す「食」食べものはもともとすべていのちのあるもの。食べるとは食べものいのちをいただくこと。海山の幸豊かな小田原の地で考える、いのちのつながりという視点での食とは・・・ |
| 6 |
いのち癒す「健康・医療・介護」日本三大茶人をはじめ、明治の元老、著名な文学者たちがこぞって住まいを求めた小田原。癒しの場であり、富裕層が老後を豊かに過ごせるリゾート地であった。森・里・海に囲まれ、風光明媚、冷涼温暖な気候、豊かな水と温泉、自然の治癒力あふれるこの小田原・箱根を、安心して家族を持ち、子育てできるまちにするためには・・・。 |
| 7 |
いのち育む「農林水産」官民連携で有機農業による里づくりをめざす小田原。水産資源豊かな相模湾の小田原沖の定置網は設備、技術とも日本随一。その里の水源である丹沢、箱根の森は同時に神奈川の魚付き林。そんな素晴らしい立地ならではの現代の自給自足とは? |
| 8 |
いのち巡る「環境」小田原の前浜からは40年前には年間50~60万尾のぶりが水揚げされていた。その後、酒匂川にダムが出来、取水堰が作られ、海岸線に沿って高速道路走り、 相模湾の生態系が変わり、今や年間数百尾の水揚げしかない。海の問題は水の問題、森の問題、そしていのちの問題にと。持続可能ないのちの循環が守れるか、まさに今が正念場。 |
| 9 |
いのち学び合う「教育」木遣りの声も高らかに神輿や山車がまちに繰り出す小田原の祭り。かつて神社や寺はまちのコミュニティ-センターであった。そこでは祭りや催事を通じ、世代を超えた学び合いがあった。まちのコミュニティが失われつつある今、地域の財産である子供を地域はどう育てるのか。 |
| 10 |
いのち宿る「美と空間」中世最大の城郭都市であった小田原。壮大な、かつ自然の理に適ったまちづくりが展開されていた。そのまちを中心に人々の交流の中で洗練されていった工芸の技。人々が集い祭ることを通じて生まれたパフォーミングアート。そんな楽しさが溢れ、世代を超えて人と人がつながるいのちの空間とは・・・。 |
| 11 |
いのち拓く「アジア」避けることができない少子化、高齢化。効率化、均一化の中で失われているかけ がいのない、地域が育んできた技や食や文化。日本の地域が直面しているこれらの問題は、全て、アジアの国々がこれから直面する問題。ここで描くモデルは世界の問題解決のソリューションになるはず。小田原モデルは世界の最先端。 |